子供のお金の教育が必要な理由|小学生からはじめたいオススメの金融教育の方法
このページにはPRリンクが含まれています
子供が将来大人になったときに適切な家計管理を行い、自立した生活を送るためには、子供のうちからお金に関する教育を行うことが大切です。日本では金融教育が十分な状況になく、学校の授業ではお金についての考え方を教えてもらえる機会が少ないため、各家庭でしっかりと教えていく必要があります。
子供の金融教育は、小学生を過ぎた頃から少しずつ始めていくことをおすすめします。そこで今回は、子供のお金の教育が必要な理由や、小学生から始めたいおすすめの金融教育の方法を分かりやすく解説します。

キッズ・マネー・ステーション代表/ファイナンシャルプランナー
キッズ・マネー・ステーション代表/ファイナンシャルプランナー 2005年からお金教育・キャリア教育を普及する「キッズ・マネー・ステーション」を主宰。2021年現在、約300名の講師たちが所属し、全国の小・中・高等学校にて授業や講演などの活動実績が多数。2017年度4月から使用される文部科学省検定の高等学校家庭科の教科書に日本のファイナンシャルプランナーとして掲載される。 著書や監修した本に「おさいふのかみさま」(フレーベル館)、「10歳から知っておきたいお金の心得」(えほんの杜)など多数。
金融教育とは
金融広報中央委員会のホームページには、金融教育について次のように書かれています。
「金融教育は、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育である。」
上記のように、金融教育とは、社会においてお金や金融がどのように作用しているのかを理解することによって、国民一人ひとりが自らの生活や日本社会についてじっくりと考えることを指しています。そしてお金について理解した上で自らの生活を豊かにしたりより良い社会を実現したりするために、自分から行動できることを目指すものです。金融教育は、人々が健全に成長していくために必要不可欠であるといえます。
子供へのお金の教育が大切な理由
子供へのお金の教育が必要になっている理由としては、次のようなものが挙げられます。
金融教育が子供に必要な理由
- 将来大人になった際の家計管理や資産形成に役立つ
- 税金や社会保障制度など世の中の仕組みの理解につながる
- 自立・自律した力が身につく
子供のうちにお金の教育を十分に実施できていた場合とそうでない場合では、将来的なお金の考え方にも大きな差がつきます。子供の成長にも大きく役立つ学びになるため、家庭できちんと取り組むことをおすすめします。ここでは、子供にとってお金の教育が大切な理由を解説します。
将来大人になった際の家計管理や資産形成に役立つ
子供にお金の教育を行うことで、将来大人になった際の家計管理に役立ちます。家計管理には、単に無駄遣いをなくすだけでなく、お金を使うときも「適切な費用・適切な金額」を支払うという意識が大切になります。子供のうちからお金を扱う経験を積み重ねておけば、無駄遣いせずに適切な家計管理を行うことができる大人に育ってくれるでしょう。
もしお金の教育を実施してこなかった場合は、下記のようなデメリットがあります。
金融教育が十分行われなかった場合
- 金銭感覚が養われず無駄使いが増える
- お金の適切な使い方が養われず、必要な時に必要なお金を使うことができなくなる
- 収入と収支のバランス感覚が培われない
- 老後や将来のために適切な資産形成ができない
このようなデメリットでお金に苦労する大人にならないためにも、金融教育は必要不可欠です。
税金や社会保障制度など世の中の仕組みの理解につながる
金融教育によって、税金や社会保障制度等、お金に関する世の中の仕組みへの理解が深まります。特に大人になってからは、下記のようなお金の流れの仕組みに苦労させられることが多いといえます。
大人になってから理解に苦労するお金の仕組みの一例
- 税金制度
- 年金制度
- 確定申告制度
- 医療・介護制度
- 資産形成投資
税金や年金制度、確定申告制度についてよく知らずにいると、支払漏れが発生したり、本来は支払う必要のない税金を多く支払ってしまったりする可能性があります。税金滞納や払い過ぎを防ぐためにも、制度を十分に理解しておくことは大切です。また、医療・介護制度や資産形成についての知識を深めることにもつながります。
自立・自律した力が身につく
お金の教育をしっかりと行うことによって、自分で考えてお金の使い方や稼ぎ方を考えられるようになるため、自立・自律した力が身につくというメリットもあります。現在の収支を鑑みて、欲しいものを我慢して支出をコントロールできるようになるだけでなく、欲しいものを買うために収入を増やすためには何をしなければならないのかを考えて行動できるようになります。
金融教育が十分に行き届いていないと、お金の使い方や稼ぎ方を考慮しないまま行き当たりばったりに欲しいものを購入してしまい、必要以上に浪費してしまったりお金が貯まらなかったりする可能性があります。
学校の授業では教えてもらえない
日本の学校においては、お金の教育が不十分であるといわれています。実際に、「日本銀行の広報活動と金融教育分野での取り組み」の中では、「学校教育においてもっと積極的にお金に関する教育に取り組んでほしい」と感じている一般の人々は57.8%にまでのぼっています。回答者の6割近くの人が学校教育だけでは金融教育が不十分だと感じています。
私たちも、大人になってから「子供の頃にこんなことを教えてくれていたら良かったのに」と思う機会はよくあるでしょう。子供にそんな思いをさせないためにも、小学生などのできるだけ早いうちからお金に関する教育を行うことをおすすめします。
お金の教育はいつから?適したタイミング
お金に関する教育を行うのは、小学校に上がった後からがおすすめです。小学生になる頃には子供の欲しいものが増えてきて、親に対して「あれが欲しい」と自分の意思を伝えるようになる機会が増えるためです。これまでは全てのタイミングで親が買い与えるかどうかを判断していたかもしれませんが、子供が自分の欲しいものを主張し始めるようになったら、金融教育を始めることを検討しましょう。
自分が欲しいものを手に入れるためにはお金が必要であることや、お金を稼ぐためには働いたり投資をしたり、何らかの行動を起こさなければならないことを学ぶ機会を設けることで、少しずつお金について考える機会を提供することが大切です。
金融教育のおすすめの教え方
お金に関する教育方法としては、下記のような方法がおすすめです。
お金に関するおすすめの教育方法
- 定額制か、報酬制(お手伝いなど対価)などの方法でおこづかいを渡す
- 子供用のお小遣い帳を記入させる
- 子供と一緒に買い物へ行く
- 投資ゲーム・アプリ・書籍を利用する
おこづかいを渡したり、お小遣い帳で収支を記録させたりする方法は、どのような過程でも比較的よく行われています。また、子供と一緒に買い物へ行く機会を増やすことも、お金に関する学びにつながるでしょう。最近では、投資ゲームやアプリを活用する家庭も増えてきています。ここでは、それぞれの金融教育の方法について詳しく解説します。
おこづかいを渡す
お手伝いなどの対価としておこづかいを渡す方法があります。子供が欲しがったものを都度買い与えたり、不定期でお小遣いを渡したりするのではなく、家事のお手伝いなどの労働対価としてお小遣いを渡すことによって、お金を得るためには対価が必要であることを理解できます。
また、対価として限りあるおこづかいを渡すことで、「お金は無限ではなく有限である」ということを分かりやすく理解できるため、「お金が足りないときは稼がなければならない」という意識が生まれやすくなります。限りあるお金を大切に使おうという気持ちも芽生えるでしょう。
一方で、定額制という渡し方があります。1週間いくらとか1か月いくらといった方法です。メリットは定額なことから、計画性を立てやすく、「少しずつ貯めて、欲しいものを購入する」といったことが実行しやすくなります。一方で、おこづかいをもらえる日が来たらお金がもらえるため、お金がどうして手に入るかという概念が薄くなります。「おうちの人が働いているから、お金が手に入るよ」という言葉を添えましょう。
子供用のお小遣い帳を記入させる
与えたおこづかいに対して、お小遣い帳を記入するように促すこともおすすめの教育方法のひとつです。お小遣い帳を記入することによって、自分がどのようなものを購入しているのか、何にいくらかかかっているのかを客観的に可視化できるため、自分のお金の使い方を振り返る機会を設けて金銭感覚を養うことが可能になります。
また、限られたお小遣いの中で欲しいものを購入する計画性を養うことができるのも、お小遣い帳のメリットです。お小遣い帳は現在の残高も把握できるため、「このペースでお金を貯めたら〇ヶ月後には欲しいものが買える」なども分かりやすくなり、「毎月〇円ずつ貯めよう!」などの意識が生まれやすくなります。
子供と一緒に買い物へ行く
子供と一緒にスーパーなどに買い物へ出かけた際に、お金について説明しながら買い物をするのは金融教育の一環として効果的です。単純に買い物に付き添わせるだけでなく、購入するものを選ぶ際に「この商品を買うためにはいくらお金が必要になるのか」を説明しながら買い物をすることによって、適切な金銭感覚を養うことができます。
日常的にお金の教育をしていれば、一般的な金銭感覚が身に付き、自然と身近にあるモノの価値を理解できるようになります。例えばフルーツを1つ購入するためにはお小遣いをどれだけ貯める必要があるのかを説明しながら買い物をするだけでも、お金の大切さを伝えられるでしょう。
投資ゲーム・アプリ・書籍を利用する
投資ゲームやアプリを利用するのも、金融教育の手段として効果的です。近年は金銭感覚を養うための子供向けのゲームやアプリが数多く登場しているため、ゲーム感覚で楽しみながら金銭感覚を養うことができます。
子供と一緒に取り組む上でおすすめの投資ゲーム・アプリとしては、「コインクロス」や「かぶポン!」などがおすすめです。「コインクロス」は硬貨を使ったクロスワードパズルで、ビギナー向けから上級者向けまで多くのステージが用意されているため、子供が初めてお金の勉強をするのにもおすすめです。また、「かぶポン!」はキャラクターを集めながらクイズ形式で金融知識が身につくため、遊びながらお金について幅広く学べるのがポイントです。
また、最近は、お金に関する書籍も多数出版されています。お金のことを取り扱った絵本も刊行されていますし、児童書もたくさん出ています。家庭では実践しづらいと思っていても、書籍を通して、親子で一緒に考えたり学んでいくことができます。児童向け書籍では、「10歳から知っておきたいお金の心得」(えほんの杜)、「ドラえもん社会ワールド お金のひみつ」(小学館)などがおすすめです。
日本よりも進んだ海外の先進国の金融教育
日本では2005年を「金融教育元年」として、日銀と政府が主導でさまざまな金融教育に取り組み始めています。主に行われている施策としては、例えば下記のようなものがあります。
金融教育元年以降、実施している取り組み事例
- 金融教育公開授業の全国展開
- 教員向けセミナー
ただし、上記の施策は海外先進国と比べると遅れており、他国ではさらに進んだ金融教育が行われています。他先進国で行われているお金に関する教育の取り組み事例には、下記のようなものがあります。
他先進国のお金に関する教育の取り組み事例
- アメリカ:パーソナルファイナンスについて学ぶためのゲームやアプリ等の教材充実
- イギリス:公立学校のカリキュラムで金融教育の必修化
- ドイツ:国やNPO法人が中心となって金融教育システム・サービスの拡充
ここでは、アメリカ、イギリス、ドイツのそれぞれの金融教育について解説します。
アメリカの事例
アメリカでは「パーソナルファイナンス」と呼ばれる「個人ごとの金融計画や管理」について学ぶことをとても大切にしています。アメリカの金融教育は州によって異なりますが、国全体で金融教育に高い意識を持っています。預貯金と投資を行うならどちらが効果的に資産を増やせるのか、それに伴うメリットやデメリットなどを学ぶことで、資産運用についての知識を子供の頃から身に付けます。
アメリカでは金融教育を行うための無料教材が充実しており、子供が気軽に遊べるゲームの中にも、借入や投資を駆使して企業を成長させていく本格的なものが数多くあります。日本でもお金に関するゲームやアプリが登場してきていますが、まだまだお金について学ぶことが当たり前であるという意識は根付いていません。
イギリスの事例
イギリスにおいては、2014年から公立学校のカリキュラムの一環として金融教育が必修科目となっています。3歳になると経済や金融について学ぶようになり、小学校卒業時にはお金と社会の関わりが理解できるように国全体で教育を行っています。
イギリスでは、4つのフレームワークを元に金融教育を進めているのが特徴的です。「お金を管理する方法」「批判的な思考ができる消費者になる」「リスクマネジメントと感情」「人々の暮らしの中で金融が果たす役割」という4つのフレームワークに基づいて論理的な教育が行われています。「お金について考える力」を養うことを重視しており、日本とは違って幼い頃から段階的な教育を行う高い計画性があります。
ドイツの事例
ドイツでは国やNPO法人が中心となって、お金について学ぶためのさまざまな外部機関やサービスが用意されています。例えば高齢者が若年層に老後資金の重要性を直接伝える「退職準備学校」や、学校の先生と生徒がお金について学ぶための「経済・銀行の学校」、フランクフルトの金融教育システムである「学校銀行」などがあります。
ドイツの金融教育は内容が多岐にわたっており、銀行やお金に関する基本だけでなく、投資・貯蓄・退職などのほか、保障やリスクの観点からお金に関する知識を学んだり、信用と負債の考え方を理解したりと、広くお金について理解できる教育内容になっているのがポイントです。連携する教育システムやサービスが充実しているのは、日本とは異なる点であるといえます。
まとめ
子供に十分なお金の教育を行うことは、お金の大切さや使い方を学ぶだけでなく、自立した精神を養って社会について考える力を身につけることにもつながります。おこづかいをあげたり、収支を記録するためにお小遣い帳をつけたりすることは金融教育の方法としてとても有効です。
まゲームやアプリ、た、近年では動画、書籍を通してお金について学べるものも増えてきているため、うまく取り入れることで子供と一緒に楽しみながらお金について学ぶことも可能です。子供の成長を促す上でも、小学生を過ぎて自分の欲しいものに興味が出てくるようになったら、家庭でお金に関する教育を始めていくと良いでしょう。
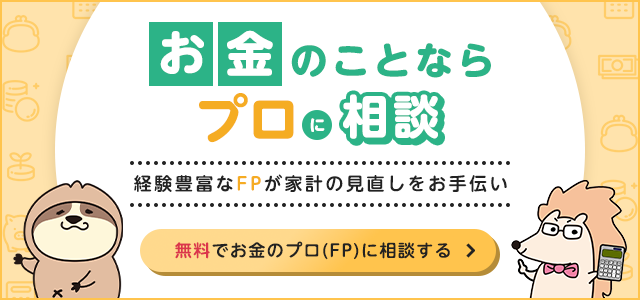
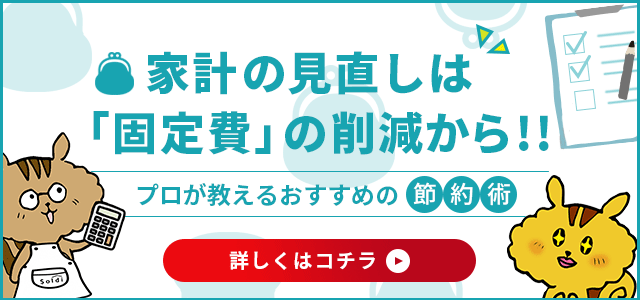
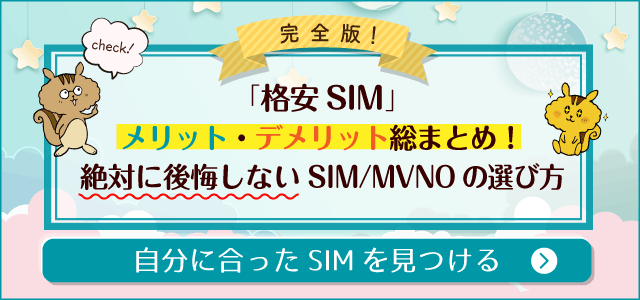
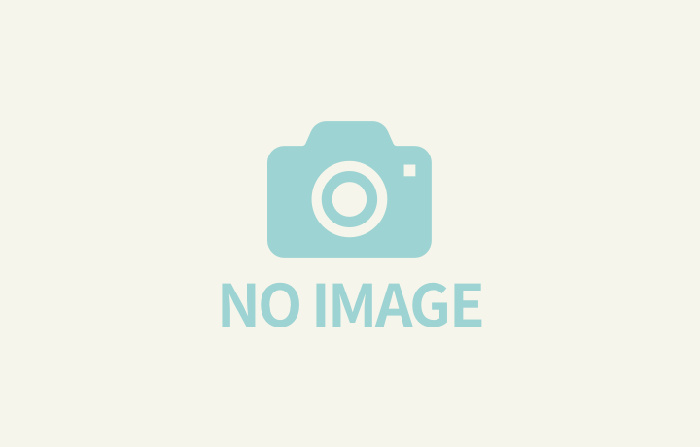


日本ではまだまだ遅れている金融教育ですが、海外ではすでに取り組まれている例をぜひお読みください。そして、「子供にはまだ早い⁉」「私には教えられないかも」と思っている親御さんも、金融教育はそれほどハードルが高い教育ではなく、まずは「お金とは何か」をお子さんに伝えてみましょう。また、近年、絵本や書籍も多数刊行され、金融教育を行っている講座やイベントもあります。ぜひきっかけづくりにしてください。おこづかい教育は家庭で行える、最も学びの大きいお金の教育です。ちょっとした工夫やコツを知って、家庭での教育を継続していただければと思います。